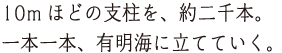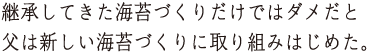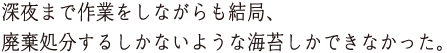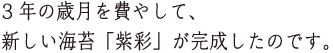有明海は、九州一の河川である筑後川が山からの栄養を注ぎ込んでいる宝の海です。有明海だけで日本の海苔の4割の生産量を誇ることからも分かるように、海苔養殖に適した海です。なぜ適しているのか、というと、それは干満の差が大きいということがあげられます。最大6mにも及ぶ干満の差によって、潮の引きとともに海苔を養殖している網は、海面から顔をだします。こうして一定の時間海苔が海面から出て空気に触れることにより乾燥させます。「干出(かんしゅつ)」と呼ばれるこの状態が海苔を強くし、病気や珪藻の繁殖から海苔を守ります。この「干出」をさせるためにも、漁師たちは約10mの支柱を、一本一本、有明海に立てていくのです。その数、二千本あまり。気が遠くなるような作業ですが、昔ながらの伝統的な製法を継承することで、他の産地にはない品質の良い「有明海苔」が生まれるのだと私たちは確信しています。

有明海の海苔畑には百数十万本の支柱が立つ。天気のいい日は支柱の向こうに遠く雲仙を臨むことができる。
しかし、そんな品質の良い有明海の海苔でさえ、時代の波にはかないませんでした。贈答品として珍重されていた時代もすぎ、大量生産の画一化された味だけが出回るようになりました。やがてバブル崩壊とともに海苔産業も傾き始めたのです。さらに平成12年には諫早湾干拓閉門が行われ、近年にない大不作の年を経験しました。祖父の代から継承してきた海苔づくりだけではダメだと祈るような想いで、父は新しい海苔づくりに挑みはじめたのです。

6mの干満の差を利用して海苔を空気にふれさせる「干出」。
父は、新しい海苔づくりに取り組み始めます。従来の四角の板海苔ではなく、素材そのままの形に近い海苔の生産に着手。先駆者の方々のところに何度も見学に行きアドバイスを乞い、試してみましたが、道のりは平坦なものではありませんでした。海という変化の激しい環境の中で、これまでとは違う新しい海苔づくりに、家族で試行錯誤を繰り返す日々。最初の何年かは、ほとんどまともな海苔が作れず、深夜まで作業をしながらも結局、廃棄処分するしかないような悔しい想いも経験しました。

海苔の収穫風景。夜に収穫された海苔は細胞が引き締まっているため、色が黒く品質がいい。
しかし、父は根気づよく海苔の開発育成を続け、決してあきらめなかったのです。失敗する度に、乾燥機の改良、作業効率の改善を繰り返していきました。そして、ようやく3年の歳月を費やして、新しい海苔「紫彩」が完成したのです。黒く艶やかで濃厚な甘みのある「紫彩」は、素材そのものの味わいが生きています。海から収穫してきた海苔をミンチで裁断し、それから和紙を漉くようにして四角いシート状に形成する従来の製法では、残念ながら海苔だけでなくそこに含まれる栄養分や旨みまで崩れてしまいます。しかし、『紫彩』はミンチで裁断せずに海苔そのままの姿で乾燥し作り上げることにより、海苔本来の栄養や旨みが生きています。また、食感や風味が最も優れている『一番摘み海苔』のみを使用。甘みがあり、口にいれたとたん、磯の香りとともに溶けていく食感を味わうことができます。

収穫し、乾燥させた状態の「紫彩」
![]()
これまでにない新しい海苔として「紫彩」は、少しずつですが話題になり、私と父に食卓を囲むお客さんと直接対話する機会も増えてきました。私たちは有明海で作業を続けながら一年の年月をかけて、一枚の海苔をつくりだします。しかしこれまで「おいしい、ありがとう」そんな言葉を直接聞くことはありませんでした。でも、漁師の手から紫彩を届けることで、初めてお客様の生の声が聞けたのです。「子どもが紫彩をかけないとご飯を食べてくれない」「お味噌汁に紫彩をいれないと物足りなくなった」などなど、嬉しい声を耳にしました。こうして最初は知り合いの店に置いてもらうだけでしたが、口コミで次第に広がっていき、ファンになってくださる方が現れたのです。大変、感謝しています。

いち漁師である私から直接、海苔をお客様に手渡すことで、私自身も変化していきました。全国の人々へと届ける責任、食べ物であるというだけではなく、日本の食文化の一旦を担っているという使命感。目には見えない多くのことを学びました。寿司という食文化が花開いた江戸時代、さらにはいにしえの奈良時代から海苔を食する習慣がありました。海苔漁師もまた伝統職人と同じなのかもしれません。食文化を支える一人として自覚した時に、三代目として、一人の海苔生産者として、私ができることは、海苔のこと、海苔がどうやって作られるか、日本一の海苔産地の有明海について、できる範囲で伝えていくことです。お客様の声、自然の声に注力しながら、これからも父譲りの妥協しないこだわりの海苔づくりを続けていきます。そして、有明海と海苔産業の未来を支えていきたい。将来、四代目の海苔漁師という選択肢も残せるよう、家族で頑張っていきたい。そう、思っています。

漁の帰りを迎えてくれる大川のシンボル、昇開橋。有明海へと注ぎ込む筑後川に建つ、東洋一の可動式鉄橋。